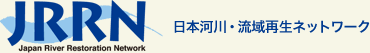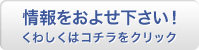< カテゴリー: 地域のカテゴリー >
五ヶ瀬川は、宮崎県と熊本県境にある向坂山を水源とする一級河川であり、下流部では、延岡市の貴重なオープンスペースとして、水面はアユ釣りやカヌー、高水敷はスポーツや散策、イベント会場として多様に利活用されています。
また、近年ではまちづくりの一環として「アスリートタウン構想」を掲げ、堤防天端及び高水敷はジョギングコースとして整備、利用されています。
加えて、秋の五ヶ瀬川では、九州最大の規模を誇る鮎やなが設けられ、やな場でアユを焼くかおりが河原を漂い、広く市民に浸透した秋の風物詩となっており、環境省の「かおり風景100選」に選ばれています。鮎やなには、年間約5万人もの観光客が訪れ、五ヶ瀬川特有の重要な観光資源となっています。
このような水環境の保全と天然アユ資源の増殖のために市民ボランティアによる河川清掃などが積極的に行われています。
なお、水の郷百選に選定されるほか、疏水百選に選ばれています。
→水の郷百選(国土交通省土地・水資源局ホームページへリンク)
→疏水百選(全国水土里ネット(全国土地改良事業団体連合会)ホームページへリンク)
By JRRN事務局 | カテゴリー: 九州 | コメント(0) | トラックバック(0)
倉敷川は、高梁川から取水される倉敷用水を水源とし児島湖に流入する2級河川です。
自然が少なくなった都市部に身近な水辺を取り戻すため、市街地中心部を流れる倉敷川は、昭和62年にふるさとの川モデル事業(現ふるさとの川整備事業)の指定を受け、親水広場である「賑わいの広場」などの整備が行われました。また、「レッドデータブック」(環境省編)の絶滅危惧Ⅱ類であるミズアオイの自生地なども保全されています。
さらに、倉敷川沿いの児島由加地区や尾原地区では、水質の保全とホタルなどの水生生物の生息環境の保全を目的として自然石による水路整備が行われました。
甦る水百選に選ばれています。
→甦る水百選(国土交通省都市・地域整備局下水道部ホームページへリンク)
By JRRN事務局 | カテゴリー: 中国 | コメント(0) | トラックバック(0)
此花西部臨海地区では「ユニバーサルスタジオ・ジャパン」を中核施設とし、ホテルや商業施設、映像情報関連施設などの都市型産業の育成を図り、大阪市の「国際集客都市づくり」の一翼を担うまちづくりが進められています。
また、安治川(旧淀川)および正蓮寺川沿いでは、スーパー堤防整備事業にあわせて臨港緑地等が整備され、豊かな水辺空間の形成が図られています。
By JRRN事務局 | カテゴリー: 近畿 | コメント(0) | トラックバック(0)
豊田川は、市内東部を流れ、天竜川へと注ぐ準用河川です。コンクリート護岸により水辺に近づくことができなかった豊田川を昔の自然な姿に蘇らせたいという思いから再生事業がスタートしました。
地域住民がワークショップという形で参画し、行政と一体となって多自然型川づくりに取り組んだ結果、地域住民の川に対する愛着が増し、河川愛護活動ともあいまって、現在は子供達で賑わう川となっています。
平成18年度手作り郷土賞に選ばれています。
→手作り郷土賞(国土交通省総合政策地域づくりホームページへリンク)
By JRRN事務局 | カテゴリー: 中部 | コメント(0) | トラックバック(0)
女鳥羽川は、松本市西部の美ヶ原に源を発し、田川に注ぐ1級河川です。 昭和63年にふるさとの川モデル事業(現ふるさとの川整備事業)に指定され、中心部の約1kmの区間を対象に平成元年から整備計画策定に着手し、平成3年に認可を受けた後、平成4年秋から中小河川改修事業(現:広域基幹河川改修事業)によって工事に着手し平成14年秋に完成しました。
市民との意見交換を積極的に行い、沿川の街並みと調和した河川として整備されただけでなく、整備後の河川を利用したイベン卜なども生まれ、市民に親しまれる川づくりが行われています。
平成13年度手作り郷土賞に選ばれているほか、「第2回関東のいい川づくり」(平成19年度)第1位に選ばれています。
By JRRN事務局 | カテゴリー: 中部 | コメント(0) | トラックバック(0)
御祓川は、七尾市南部山地に源を発し、七尾湾に流入する2級河川です。
中心市街地の活性化を目指して、七尾都市ルネッサンス都心軸整備計画が立案され、駅前から御祓川河口の港湾部までの都心軸づくりが進められています。平成11年度に中心市街地内の区間1,230mをふるさとの川整備事業の認定を受け、アメニティ性の高い水辺空間整備を行っています。
→日本水大賞((社)日本河川協会のホームページへリンク)
→全建賞 御祓川ふるさとの川整備事業はこちら(社団法人全日本建設技術協会ホームページへリンク)
By JRRN事務局 | カテゴリー: 北陸 | コメント(0) | トラックバック(0)
金沢市は犀川・浅野川という二つの川と三つの丘で構成される自然地形的特性を持ち、加賀百万石の伝統的な町並みが残る町です。こうした自然的環境と歴史的環境を「伝統環境」として位置づけ、早くから景観の保存・育成に取り組んできました。
犀川と浅野川は、景観条例や都市マスタープランに「伝統環境保存区域」として明確に位置づけられ、周辺の街並みや斜面緑地を含むきめ細かな保全対策がとられています。
昭和61年度、昭和62年度、及び平成2年度に「手作り郷土賞」に選ばれています。
→「手作り郷土賞」昭和61年度(国土交通省総合政策地域づくりホームページへリンク)
→「手作り郷土賞」昭和62年度(国土交通省総合政策地域づくりホームページへリンク)
→「手作り郷土賞」平成2年度(国土交通省総合政策地域づくりホームページへリンク)
By JRRN事務局 | カテゴリー: 北陸 | コメント(0) | トラックバック(0)
引地川は、その源を大和市の「泉の森」内に水源を発し、相模湾に注ぐ流路延長約17kmの二級河川です。
昭和52年頃の河川改修によりコンクリート三面張りの水路となりましたが、多自然型川づくり事業により、川沿いに残る斜面緑地や公園のオープンスペースを活かして、昔なつかしい小川が復元されました。
河道と低水路を蛇行させて瀬や淵をつくり、河岸には植生の生育が可能な工法を採用しているため、植生が繁茂しました。水際のよどみには多くの小魚が生息し、水遊びやザリガニ取りをする子供達が集まり、ふるさとの小川の姿を取り戻しています。
昭和63年度手作り郷土賞に選ばれています。
→手作り郷土賞(国土交通省総合政策地域づくりホームページへリンク)
By JRRN事務局 | カテゴリー: 関東 | コメント(0) | トラックバック(0)
信濃川河口付近には、水辺空間を生かし緑地帯として河岸を整備した「やすらぎ堤」があります。市政100周年記念植樹祭で植えられた桜と柳の並木が続き、市民の憩いの場となっており、日中はサイクリングやジョギングを楽しむ人、春は花見、夏は花火見物と、いつも大勢の人で賑わっています。
新潟市内は川や海の水面の高さより土地が低いゼロメートル地帯が広がっており、洪水や津波に対して弱い地域です。そこで、防災面はもちろん、人々が集い、憩える街なかのやすらぎの場として堤防整備が始まり、全長約4.5kmの河川整備事業が計画されており現在も整備は進行中です。
昭和61年度、平成2年度「手作り郷土賞」に選ばれています。
→「手作り郷土賞」昭和61年度(国土交通省総合政策地域づくりホームページへリンク)
→「手作り郷土賞」平成2年度(国土交通省総合政策地域づくりホームページへリンク)
→「手作り郷土賞」平成2年度(国土交通省総合政策地域づくりホームページへリンク)
By JRRN事務局 | カテゴリー: 北陸 | コメント(0) | トラックバック(0)
名取川支川の広瀬川は、市民の憩いの場として年間を通じて親しまれ、8月には「灯籠流し」や花火大会も実施され、「杜と水の都”仙台”」の象徴となっています。
仙台市街地は、藩政時代、生活用水や農業用水として市民生活を支えるために、名取川・広瀬川から導水するために建設された堀や水路が今も残っています。この水路も、都市化による生活排水の流入や水利用形態の変化によって水環境が悪化していましたが、昭和49年に「広瀬川の清流を守る条例」を制定し、市民との協働により水質浄化や景観・自然環境の保全に取り組み、川を軸とした”まちづくり”として、修繕事業などの取組みが注目されています。加えて、堀を活用した広瀬川への環境用水の導水も行われています。
こうした取組みの結果、広瀬川は「21世紀に残したい日本の自然100選」や「名水100選」「日本の音風景百選」に選ばれるなど高い評価を受け、今日では全国的に名を知られる、市民共有の貴重な財産となっております。
→名水百選(環境省ホームページへリンク)
By JRRN事務局 | カテゴリー: 東北 | コメント(0) | トラックバック(0)