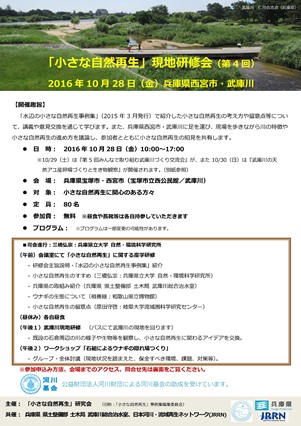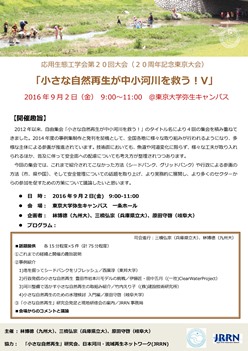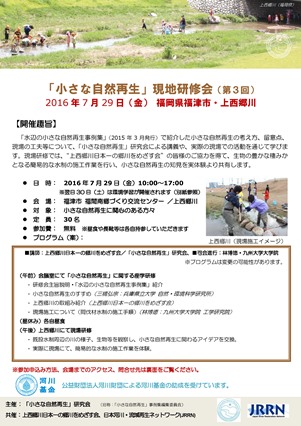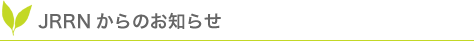
< JRRNからのお知らせ トップページ >

JRRN歓迎ボード

準備会議の様子

会議終了後の集合写真
2016年11月29日(火)、JRRN事務局より2名が中国・北京にある「中国水利水電科学研究院(IWHR)」を訪問し、ARRNの中国窓口であるCRRN事務局及び国際水圏環境工学会(IAHR)北京事務局と、来年のアジア河川・流域再生ネットワーク(ARRN)年次行事に向けた準備協議を行いました。
本準備会議は、本年8月に韓国・仁川市で開催した「第11回ARRN運営会議」において、①ARRN事務局を2017年夏よりJRRNが再び担うこと、また②来年度ARRN年次行事(第12回ARRN運営会議、第14回ARRN国際フォーラム)を2017年8月にマレーシアで行われる「第37回・国際水圏環境工学会世界会議 (IAHR 2017)」と合わせて開催する仮決定を受けて開かれたものです。
本準備会議において、来年度ARRN年次行事をIAHR2017に合わせて開催することが決定し、アジアの河川再生の知見を共有するとともに、多くのアジアの関係者がARRN活動に参加頂けるよう、IAHR副会長、IAHR北京事務局長及びCRRN事務局メンバーとともに、IAHRとARRNの連携のあり方や今後の準備内容等について調整を行いました。
2017年のARRN年次行事の概要が定まりましたら、改めて皆様にご紹介致します。
※第37回・国際水圏環境工学会世界会議 (IAHR 2017)ホームページ:
https://www.iahr.org/worldcongress2017
By JRRN事務局 | カテゴリー: ARRN会議報告 | コメント(0) | トラックバック(0)
|
日時: 2016年12月01日 18:09
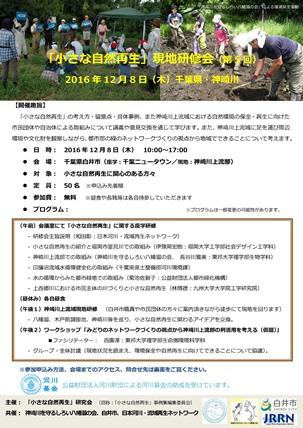 第5回「小さな自然再生」現地研修会 案内チラシ(PDF 660KB)
第5回「小さな自然再生」現地研修会 案内チラシ(PDF 660KB)
第5回「小さな自然再生」現地研修会を、2016年12月8日(木)に千葉県白井市内の神崎川上流部にて開催致します。
本研修会では、「小さな自然再生」の考え方・留意点・具体事例、また神崎川上流域における自然環境の保全・再生に向けた市民団体や自治体による取組みについて講義や意見交換を通じて学びます。また、神崎川上流域に足を運び周辺環境や文化財を観察しながら、都市部の緑のネットワークづくりの視点から地域でできることについて考えます。(平成28年度河川基金助成事業)
第5回「小さな自然再生」現地研修会 千葉県・神崎川
【日時】2016年12月8日(木)10:00~17:00
【主催】「小さな自然再生」研究会 ※(旧称:「小さな自然再生」事例集編集委員会)
【共催】神崎川を守るしろい八幡溜の会、白井市、日本河川・流域再生ネットワーク(JRRN)
【会場】千葉ニュータウン・プラザ西白井1番街団地集会所(北総線・西白井駅から徒歩3分)
【対象】小さな自然再生に関心のある方々
【定員】 50名(申込先着順)
【参加費】 無料 (昼食や長靴等は各自持参)
【プログラム(案)】
(午前)会議室にて「小さな自然再生」に関する座学研修
- 研修会主旨説明
(和田彰:日本河川・流域再生ネットワーク)
- 小さな自然再生の紹介と福岡市室見川での取組み
(伊豫岡宏樹:福岡大学工学部社会デザイン工学科)
- 神崎川上流部での取組み
(神崎川を守るしろい八幡溜の会、 長谷川雅美:東邦大学理学部生物学科)
- 印旛沼流域水循環健全化の取組み
(千葉県県土整備部河川環境課)
- 水の循環からみた都市緑地での取組み
(菊池佐智子:公益財団法人都市緑化機構)
- 上西郷川における市民主体の川づくりと小さな自然再生
(林博徳:九州大学大学院工学研究院)
(昼休み)各自昼食
(午後1)神崎川上流域現地研修
※白井市職員や市民団体の方々に案内頂きながら徒歩にて現地を回ります。
- 八幡溜、木戸前調節池、神崎川等を巡り、小さな自然再生に関わるアイデアを交換。
(午後2)ワークショップ
■ファシリテーター: 西廣淳:東邦大学理学部生命圏環境科学科
■テーマ: みどりのネットワークづくりの視点から神崎川上流部の利活用を考える(仮題)
- グループ・全体討議(現地状況を踏まえ、環境保全や自然再生に向けてできることについて協議)。
【参加申込方法】
以下の案内チラシ裏面の必要事項を明記の上、EmailまたはFAXでお申込み下さい。
※申込〆切: 12月2日(金)午後5時まで(申込多数の場合は先着順とさせて頂きます)
「小さな自然再生」の更なる推進に向け、皆様のご参加をお待ちしております。
※現地研修会案内チラシはこちら(PDF 660KB)
By JRRN事務局 | カテゴリー: JRRN行事開催案内 | コメント(0) | トラックバック(0)
|
日時: 2016年11月15日 16:51
 JRRN/ARRN設立10周年記念メッセージ(PDF 1.1MB)
JRRN/ARRN設立10周年記念メッセージ(PDF 1.1MB)
『アジア河川・流域再生ネットワーク(ARRN)』 及びARRNの日本窓口を担う『日本河川・流域再生ネットワーク(JRRN)』は、2016年11月9日(水)に設立10周年を迎えました。
会員皆様へ、JRRN顧問及び理事よりメッセージをお届けします。
■皆様へのメッセージはこちらから(PDF 1.1MB)
日本及びアジアの川づくりの担い手による新たな価値共創の場づくりを目指し更に頑張って参りますので、今後ともご支援・ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
JRRN事務局一同
By JRRN事務局 | カテゴリー: JRRN理事会報告,その他 | コメント(0) | トラックバック(0)
|
日時: 2016年11月09日 11:11
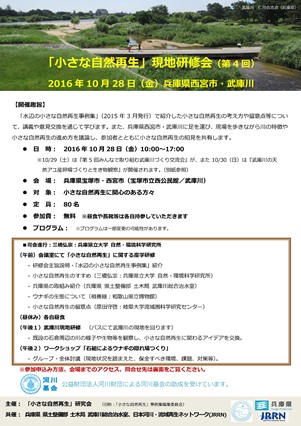 第4回「小さな自然再生」現地研修会 案内チラシ(PDF 458KB)
第4回「小さな自然再生」現地研修会 案内チラシ(PDF 458KB)
第4回「小さな自然再生」現地研修会を、2016年10月28日(金)に兵庫県武庫川にて開催致します。
本研修会では、「水辺の小さな自然再生事例集」(2015年3月発行)で紹介した小さな自然再生の考え方や留意点、現地での取組みやウナギの生態等について講義や意見交換を通じて学びます。また、兵庫県・武庫川に足を運び、現場を歩きながら川の特徴や小さな自然再生の進め方を議論し、参加者とともに小さな自然再生の知見を深めます。(平成28年度河川基金助成事業)
第4回「小さな自然再生」現地研修会 兵庫県・武庫川
【日時】2016年10月28日(金)10:00~17:00
【主催】「小さな自然再生」研究会 ※(旧称:「小さな自然再生」事例集編集委員会)
【共催】兵庫県県土整備部土木局武庫川総合治水室、日本河川・流域再生ネットワーク(JRRN)
【会場】兵庫県宝塚市 及び 西宮市(座学:宝塚市立西公民館/現地:武庫川)
※宝塚市立西公民館:兵庫県宝塚市小林2丁目7番30号
【対象】小さな自然再生に関心のある方々
【定員】 80名(申込先着順)
【参加費】 無料 (昼食や長靴等は各自持参)
【プログラム(案)】
■司会進行: 三橋弘宗:兵庫県立大学 自然・環境科学研究所
(午前)会議室にて「小さな自然再生」に関する座学研修
- 研修会主旨説明・「水辺の小さな自然再生事例集」紹介
- 小さな自然再生のすすめ(三橋弘宗:兵庫県立大学 自然・環境科学研究所)
- 兵庫県の取組み紹介(兵庫県 県土整備部 土木局 武庫川総合治水室)
- ウナギの生態について(揖善継:和歌山県立自然博物館)
- 小さな自然再生の留意点(原田守啓:岐阜大学流域圏科学研究センター)
(昼休み)各自昼食
(午後1)武庫川現地研修 (バスにて武庫川の現地を回ります)
- 仁川合流点周辺の様子、落差工の簡易魚道等を巡り、小さな自然再生のアイデアを交換。
(午後2)ワークショップ「魚類の生息・遡上環境の改善~ウナギ石組や落差工対策」
- グループ・全体討議(現地状況を踏まえ、石組みによるウナギ等の生息場保全や落差工対策について協議)。
【参加申込方法】
以下の案内チラシ裏面の必要事項を明記の上、EmailまたはFAXでお申込み下さい。
※申込〆切: 10月20日(木)午後5時まで(申込多数の場合は先着順とさせて頂きます)
※現地研修会案内チラシはこちら(PDF 458KB)
「小さな自然再生」の更なる推進に向け、皆様のご参加をお待ちしております。
<翌日10/29(土)には子ども達による石組みの実演もあります>
研修会翌日の10/29(土)には兵庫県主催『第5回みんなで取り組む武庫川づくり交流会』が開催され、子ども達による石組みが実演されます。
第4回現地研修会に参加される方々は、翌日も子ども達のサポーターとして実際の石組み作業に協力頂けますので、本交流会の詳細は以下の兵庫県ホームページをご覧ください。
(協力者の申込みは不要。参加者は現地研修会当日に確認致します。)
■『第5回みんなで取り組む武庫川づくり交流会』案内ページはこちらから
By JRRN事務局 | カテゴリー: JRRN行事開催案内 | コメント(0) | トラックバック(0)
|
日時: 2016年09月23日 17:19


第11回ARRN運営会議の様子
 会議終了後の記念撮影
会議終了後の記念撮影
2016年8月24日(水)に、アジア河川・流域再生ネットワーク(ARRN)の「第11回運営会議」が第12回水理情報学国際会議(HIC2016)に合わせて韓国・仁川市にて開催され、日中韓の各RRNメンバーに加え、イランやベトナムなどARRN会員以外の国々もオブザーバー参加しました。
本年の運営会議では、ARRN会長 及び 韓国国土交通部・河川運営課長の挨拶から始まり、ARRN規約に基づき以下の活動報告と審議が行われました。
<報告>
・JRRN(日本), CRRN(中国), KRRN(韓国)の過去1年間の活動概要報告
<審議>
・2017年のARRN活動計画について
・来期(2017年夏以降)のARRN事務局移管について
・ARRNと韓国国土交通部との今後の連携について
・ARRNの更なるネットワーク拡大について
運営会議の開催報告概要はJRRNニュースレター10月号で改めてご紹介させて頂きます。
→第11回運営会議「議事次第」及び「参加者名簿」(英語版)はこちら(PDF 56KB)
→JRRNニュースレター2016年10月号はこちら ※未作成
<過去の運営会議はこちらから>
→第10回運営会議開催報告はこちら(2015年4月・韓国/慶州開催)
→第9回運営会議開催報告はこちら(2014年11月・ウィーン開催)
→第8回運営会議開催報告はこちら(2013年9月・成都開催)
→第7回運営会議開催報告はこちら(2012年11月・北京開催)
→第6回運営会議開催報告はこちら(2011年11月・東京開催)
→第5回運営会議開催報告はこちら(2010年9月・韓国・ソウル開催)
→第4回運営会議開催報告はこちら(2009年9月・韓国・ソウル開催)
→第3回運営会議開催報告はこちら(2008年11月・中国・北京開催)
→第2回運営会議開催報告はこちら(2007年12月・東京開催)
By JRRN事務局 | カテゴリー: ARRN会議報告 | コメント(0) | トラックバック(0)
|
日時: 2016年08月29日 12:22
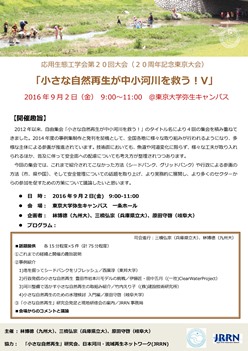 小さな自然再生が中小河川を救う!V 案内チラシ(PDF 486KB)
小さな自然再生が中小河川を救う!V 案内チラシ(PDF 486KB)
JRRNでは、「小さな自然再生」研究会(旧称:「小さな自然再生」事例集編集委員会)の協力を得ながら、「水辺の小さな自然再生事例集」を全国に普及するとともに、本分野の情報交換や交流のコミュニティを構築し、小さな自然再生の仲間と裾野を拡げるための普及促進活動を継続的に実施しています。
昨年度に引き続き、今年で5回目となる以下の行事が、応用生態工学会 第20回大会(東京大会) で開催されますので、皆様にご案内させて頂きます。
応用生態工学会第20回大会 自由集会「小さな自然再生が中小河川を救う!V」
【日時】 9月2日(金) 9:00~11:00
【場所】 東京大学弥生キャンパス 一条ホール
【企画】 林博徳(九州大)、三橋弘宗(兵庫県立大)、原田守啓(岐阜大)
【開催趣旨】
2012年以来、自由集会「小さな自然再生が中小河川を救う!」のタイトル名により4回の集会を積み重ねてきました。2014年度の事例集制作と発刊を契機として、全国各地に様々な取り組みが行われるようになり、多様な主体による参画が推進されています。技術面においても、魚道や河道変化に限らず、様々な工夫が取り入れられるほか、普及に伴って安全面への配慮についても考え方が整理されつつあります。
今回の集会では、これまで紹介されてこなかった方法(シードバンク、グリッドバンク)や行政による参画の方法(市、県や国)、そして安全管理についての話題を取り上げ、より実務的に展開し、より多くのセクターからの参加を促すための方策について議論したいと思います。
【プログラム】 (司会進行:三橋弘宗、林博徳)
■話題提供: 各15分程度×5件(計75分程度)
①これまでの経緯と開催の趣旨説明
②事例紹介
1)池を掘ってシードバンクをリフレッシュ/西廣淳(東邦大学)
2)行政発信の小さな自然再生 豊田市岩本川モデルの挑戦
/山本大輔(豊田市矢作川研究所)&伊藤匠((一社)ClearWaterProject)
3)河川整備で活かす小さな自然再生の取組み紹介/竹内えり子((株)建設技術研究所)
4)小さな自然再生のための水理検討 入門編/原田守啓(岐阜大学)
③「小さな自然再生」研究会発足と現地研修会の案内/後藤勝洋(JRRN事務局)
■会場からのコメントと議論
※「応用生態工学会第20回大会(20周年記念東京大会)」プログラム詳細は応用生態工学会ホームペ-ジをご覧ください。
http://www.ecesj.com/contents/event/conference/20th/20th_meet.html
By JRRN事務局 | カテゴリー: JRRN行事開催案内 | コメント(0) | トラックバック(0)
|
日時: 2016年08月02日 15:50
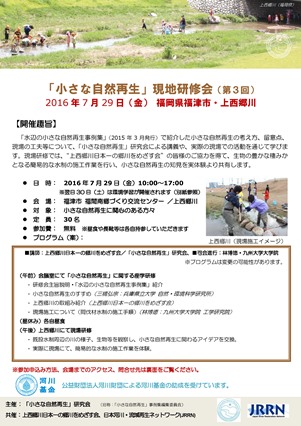 第3回「小さな自然再生」現地研修会 案内チラシ(PDF 885KB)
第3回「小さな自然再生」現地研修会 案内チラシ(PDF 885KB)
今年度初回となります第3回「小さな自然再生」現地研修会を、2016年7月29日(金)に福岡県福津市・上西郷川にて開催致します。
本研修会では、「水辺の小さな自然再生事例集」(2015年3月発行)で紹介した小さな自然再生の考え方、留意点、現場の工夫等について、「小さな自然再生」研究会による講義や、実際の現場での活動を通じて学びます。現場研修では、“上西郷川日本一の郷川をめざす会”の協力を得て、生物の豊かな棲みかとなる簡易的な水制の施工作業を行い、小さな自然再生の知見を実体験より共有します。(平成28年度河川基金助成事業)
第3回「小さな自然再生」現地研修会 福岡県福津市・上西郷川
【日時】2016年7月29日(金)10:00~17:00
※翌日7/30(土)には環境学習「川遊び探険と灯明づくり in 上西郷川」が開催されます。
【主催】「小さな自然再生」研究会 ※(旧称:「小さな自然再生」事例集編集委員会)
【共催】上西郷川日本一の郷川をめざす会、日本河川・流域再生ネットワーク(JRRN)
【会場】福岡県福津市(福間南郷づくり交流センター/上西郷川)
※福間南郷づくり交流センター:福岡県福津市日蒔野4丁目19番地の1
【対象】小さな自然再生に関心のある方々
【定員】 30名(申込先着順)
【参加費】 無料 (昼食や長靴等は各自持参)
【プログラム(案)】
■講師: 上西郷川日本一の郷川をめざす会/「小さな自然再生」研究会
(午前)会議室にて「小さな自然再生」に関する座学研修
- 研修会主旨説明・「水辺の小さな自然再生事例集」紹介
- 小さな自然再生のすすめ(三橋弘宗:兵庫県立大学 自然・環境科学研究所)
- 上西郷川の取組み紹介(上西郷川日本一の郷川をめざす会)
- 現場施工について(間伐材水制の施工手順)(林博徳:九州大学大学院 工学研究院)
(昼休み)各自昼食
(午後)上西郷川にて現場研修
- 既設水制周辺の川の様子、生物等を観察し、小さな自然再生に関わるアイデアを交換。
- 実際に現場にて、簡易的な水制の施工作業を体験。
【参加申込方法】
以下の案内チラシ裏面の必要事項を明記の上、EmailまたはFAXでお申込み下さい。
※申込〆切: 7月26日(火)午後5時まで(申込多数の場合は先着順とさせて頂きます)
※現地研修会案内チラシはこちら(PDF 885KB)
By JRRN事務局 | カテゴリー: JRRN行事開催案内 | コメント(0) | トラックバック(0)
|
日時: 2016年07月11日 16:32

日本河川・流域再生ネットワーク(JRRN)の『平成28年度 第1回理事会』が下記の通り開催され、全議案が承認されました。
本年11月にJRRNが設立10年を迎えることを踏まえ、今後の更なる発展に向けた活動内容や組織のあり方などについて活発な議論が行われました。
1. 開催日時: 2016年6月3日(金) 16:00-17:30
2. 開催場所: (公財)リバーフロント研究所 会議室
3. 理事総数: 4名(内、1名はJRRN定款第26条に基づく書面表決)
4. 議案:
議案第1号 平成27年度 事業報告及び収支決算 (PDF 205KB)
議案第2号 平成28年度 事業計画及び収支予算 (PDF 938KB)
報告第1号 事務局の組織及び運営
その他
※参考: JRRN定款 (PDF 112KB)
By JRRN事務局 | カテゴリー: JRRN理事会報告 | コメント(0) | トラックバック(0)
|
日時: 2016年06月06日 11:14
今年で7年目を迎えました「桜のある水辺風景」が、Facebookからも投稿できるようになりました。
 「桜のある水辺風景写真2016」Facebookページはこちらから
「桜のある水辺風景写真2016」Facebookページはこちらから
○テーマ: 「桜のある水辺風景 2016」
○応募資格: どなたでもご応募いただけます。
○応募期間: 2016年3月23日(水)~2016年5月18日(水)
○facebook投稿の作品規定:
・ご本人が2016年に撮影された写真に限定します。
・写真データは5MB以内、横1600px × 縦1600px以内を目安として下さい。
・応募作品数の制限はございません。但し、ご本人が撮影した写真に限定します。
・個人が特定できる画像が含まれる場合は被写体の方の了承を得て下さい。
○facebook投稿方法:
・「桜のある水辺風景」facebookページから、ご本人のアカウントでログインしてください。
・Facebookのタイムラインの投稿欄の[写真・動画]から写真を投稿して下さい。
・[コメント欄]に、撮影場所(河川名等)やメッセージ(作品への思いなど)を自由に入力してください。
・[投稿する]のボタンをクリックしてください。(これで完了です)
○facebookでの表示方法:
・Facebookのタイムライン投稿後は、ページ左の「ビジター投稿」欄にリアルタイムで掲載されます。
・投稿頂いた作品は、JRRN事務局でFacebookのタイムラインページ上に「写真」「コメント」「氏名」とともに数日以内にアップしてご紹介させて頂きます。
○facebookの削除方法:
・Facebookへの投稿後、「ビジター投稿」欄の右上より、ご自分の投稿を削除することができます。
・タイムラインページ上に掲載された作品の削除を希望する場合は、JRRN事務局(info@a-rr.net)までお知らせ下さい。
○応募作品の取扱い:
・Facebookページ及び「桜のある水辺風景2016 応募写真集」の中でご紹介させて頂きます。
・応募作品を紹介する際には氏名も掲載させて頂きます。
・上記のご紹介に際しては、同一地点での類似した風景等の作品は事務局により掲載作品を選ばせて頂く場合があります。
・応募内容が本企画趣旨に沿わないと判断した場合は紹介を控えさせて頂くことがあります。
・JRRNの刊行物やウェブサイト等で使用させて頂くことがあります。
○問合せ先:
〒104-0033 東京都中央区新川1丁目17番24号 新川中央ビル7階 (公財)リバーフロント研究所内
日本河川・流域再生ネットワーク(JRRN) 事務局
担当:阿部・和田(Eメール: info@a-rr.net )
By JRRN事務局 | カテゴリー: その他 | コメント(0) | トラックバック(0)
|
日時: 2016年03月23日 16:41
 「桜のある水辺風景写真2016」Facebookページはこちらから
「桜のある水辺風景写真2016」Facebookページはこちらから
 応募案内チラシ(PDF 741KB)
応募案内チラシ(PDF 741KB)
本企画も7年目を迎えました。
皆様が2016年に撮影された「桜のある水辺風景」の写真とメッセージを今年も募集致します。
沖縄から北海道まで、日本の魅力を再発見できるような素敵な桜のある水辺写真をお待ちしております。
なお、今年からFacebookでのご応募も可能となりました。従来通り事務局にメールや郵送でご応募頂いた作品もFacebookでご覧頂けます。
Facebookでの応募方法は以下をご覧ください。
→Facebookでの応募方法についてはこちら(ここをクリック)
「桜のある水辺風景 2016」 応募要項 (Eメール応募用)
○テーマ:「桜のある水辺風景 2016」 ※2016年に撮影された写真限定
○応募資格: どなたでもご応募いただけます(JRRN会員・非会員)
○作品規定:
・ご本人が撮影したデジタル写真(3MB以内/枚)のみの投稿とさせて頂きます。
・応募はお一人5点まで可能です。
・個人が特定できる画像が含まれる場合は被写体の方の了承を得て下さい。
○応募方法:
以下の「応募シート」に、題名、撮影場所、撮影年月、メッセージ(作品への思い等)、氏名、Eメールアドレスをご記入の上、写真と共にEメールで送付下さい。
※応募シート: http://www.a-rr.net/jp/info/letter/docs/Photo2016form.doc
※Eメールで複数画像を送付する場合、合計サイズが約3MB以下となるよう複数回に分けて送付をお願いします。
○応募期間: 2016年3月23日(水)~2016年5月18日(水)
○応募作品の取扱いについて:
・Facebookページ及び「桜のある水辺風景2016 応募写真集」の中でご紹介させて頂きます。
・応募作品を紹介する際には氏名も掲載させて頂きます。匿名での紹介を希望される方は、応募シート内「⑦その他」の欄にその旨をご記載下さい。
・同一地点での類似した風景等の作品は事務局により写真集掲載作品を選ばせて頂く場合があります。
・応募内容が本企画趣旨に沿わないと判断した場合は紹介を控えさせて頂くことがあります。
・JRRNの刊行物やウェブサイト等で使用させて頂くことがあります。
・応募作品は返却致しませんのでご了承ください。
○応募先(問合せ):
〒104-0033 東京都中央区新川1丁目17番24号 新川中央ビル7階 (公財)リバーフロント研究所内
日本河川・流域再生ネットワーク(JRRN) 事務局
担当:阿部・和田(Eメール: info@a-rr.net )
○個人情報の取り扱いについて
ご記入頂いた個人情報は、作品使用に関するお問い合わせ時に利用させて頂きますが、他の目的で利用することはございません。
皆様からのたくさんのご応募をお待ちしております。
→企画チラシ(含:応募シート)はこちら(PDF 741KB)
→応募シート(Wordファイル)のダウンロードはこちら(Ms-Word 55KB)
→『桜のある水辺風景写真集』全バックナンバーはこちら(2010年-2015年)
By JRRN事務局 | カテゴリー: その他 | コメント(0) | トラックバック(0)
|
日時: 2016年03月23日 16:35
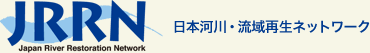





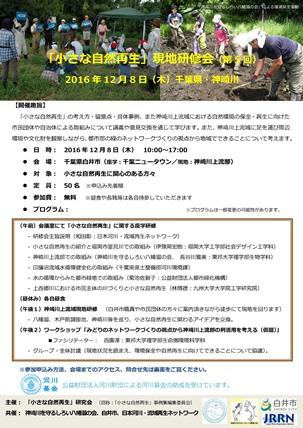 第5回「小さな自然再生」現地研修会 案内チラシ(PDF 660KB)
第5回「小さな自然再生」現地研修会 案内チラシ(PDF 660KB)