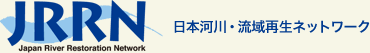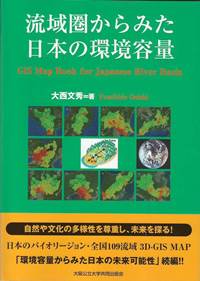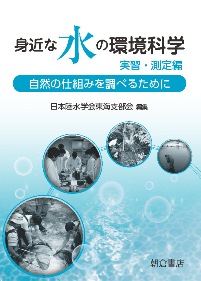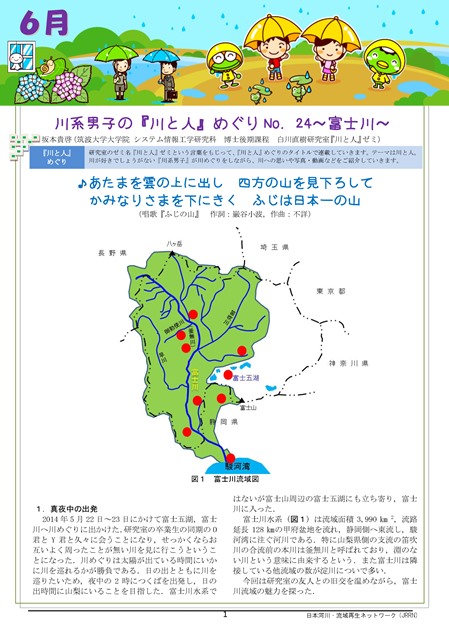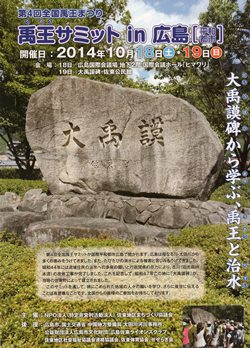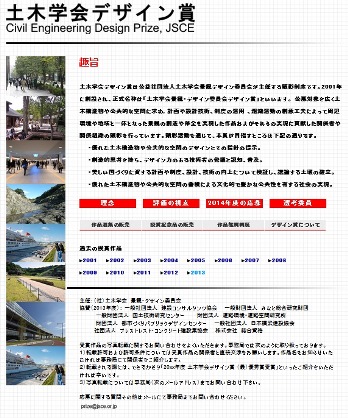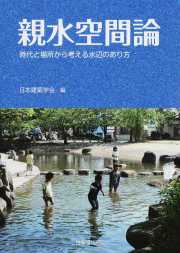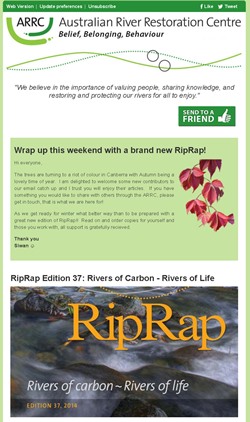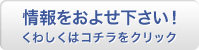受賞記念「流域圏からみた日本の環境容量」新刊書籍&謝恩案内
大西文秀様(JRRN個人会員)より、全国109水系の流域を対象にした『流域圏からみた日本の環境容量』の出版及び謝恩割引のご案内を頂きました。
●書名: 流域圏からみた日本の環境容量-日本のバイオリージョン・全国109流域 3D-GIS MAP-
●著者: 大西文秀
●判型: B5、上製本
●頁数: 222、オールカラーページ
●ISBN: 978-4-907209-08-7 C3051
●定価: 本体価格3,200円 + 税
●出版社:大阪公立大学共同出版会・OMUP
(以下、詳しい案内文です)
By JRRN事務局 | カテゴリー: 会員からの書籍・資料案内 | コメント(0) | トラックバック(0)
|
日時: 2014年06月13日 14:57